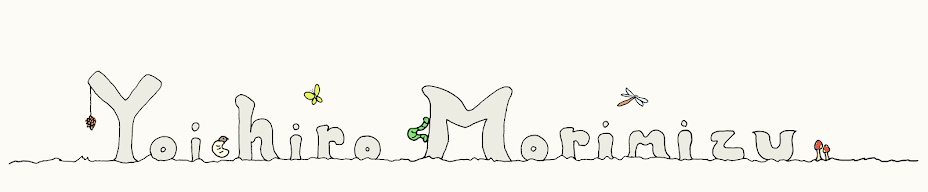去年の夏、丹波にある立杭焼の窯場で、ちょっとした陶芸体験をしてきました。
本来なら、窯場におまかせするかたちで、作品に釉薬をほどこしてもらうのですが、そこはかたくなに、いくらか怪訝な顔をされながらも、あえて土味を残した、すっぴんの焼き締めにしてもらいました。といっても、赤松の薪による伝統的な登り窯ではなく、観光客向けの電気窯での処理になるので、ビードロ状の自然釉の景色は、はなから期待できなかったのですが。
庭先に、モグラの露天風呂を思わせる 地面に穴を掘ったかたちの石組みの地炉(じろ)はあるのですが、インターネットであれこれ調べたかぎり、縄文式の野焼きでは、温度管理がなかなか難しそう。
そこでさっそく、近所のホームセンターに出向き、七輪や大量の炭、耐火レンガや保護ゴーグル、乾燥させた作品を遠火であぶるための金網などを買い込んできました。
強度の関係でしょうか、七輪の内部は思いのほかせまく、内壁の珪藻土をノミでがんがん削っていきます。それでも収まるサイズは、どんぶり茶碗ぐらいが限度。そのころには、あらたな目標ができており、頭の中であれこれ完成形を思い描きつつ、加工前の牛革なども取り寄せていました。
その後、予期せぬ爆発や、冷ましでのひび割れなどをくぐり抜けて、秋終わりにようやく仕上がったのが、こちら。
ちなみに、革の小袋のえんじ色は、詩集のワンポイント、および見返しの紙の色とリンクしています。もちろん、革ひもの留め具も自作。購入時にざらついていた革の裏面は、クリーム状のトコノールをすりこみ、ガラスコップの裏面で親のかたきのごとく、徹底的に磨き上げました。
革の小袋のなかでは、当然ふたが暴れ、へたをすると割れてしまうので、黄色いウコン布で包んで収納。そしていざ、12月の終わり、四ツ谷の北島亭へとくり出し、ささやかなお祝い会の席にて、薔薇色の歓声を浴びつつ、お披露目することができたのでした。
実は中に、ちょっとした「福の神」を忍ばせていたのですが、それは秘密。(ブログ経由で詩集『九月十九日』を購入すると、いくつか特典がついてくるので、その答えを知ることができます)
【追記・すでに終了し、現在のおまけは陶器製の小玉ヒツジ】
【追記・すでに終了し、現在のおまけは陶器製の小玉ヒツジ】
数が二つ多いのは、拭き漆(うるし)のボールペンを贈って下さった、ふらんす堂の社長、山岡喜美子さんと、すでに個人蔵となっていた表紙の絵を、再撮影にあたりこころよく提供して下さった、持ち主の方への御礼。
そうして、詩集の刊行までに、いろいろと予期せぬ荒波が待ち受けていながらも、なんとか心強い三銃士とともに、ダルタニアンは三位一体ならぬ、四位一体となって、ささやかな冒険の旅を、無事に終えたのでした。