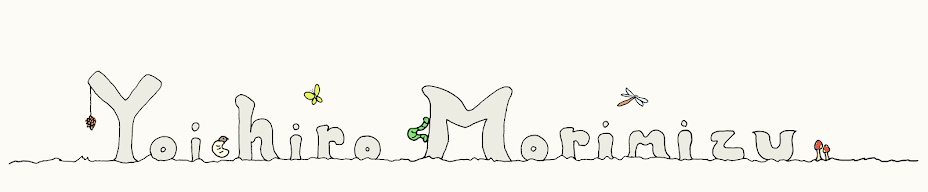千葉の特産と聞かれて、ガラス製品と答える人はまずいないだろう。その道に明るい人であれば、「九十九里にかの有名な、スガハラがあるじゃないか」と、口をとがらすのかもしれないが。
なかなかワイルドなお人柄で、このページを見てもらえればわかるとおり、福田さんのガラス炉は、その大部分が自作だ。耐火キャスターで型どりをし、骨組みの溶接までしている。工房内の一角には、さらに驚くべき秘密が隠されているのだが、プライバシーのこともあるのでここには記さない。(実際に吹きガラスの体験をすれば、おそらく知ることができます)
おいおい、九十九里のガラスと言えば、あの人を忘れてないか。という声があるのかは疑問だが、もう一人、紹介したい人がいる。
沖縄や兵庫の丹波など、いろいろな場所で生活されていた左藤さんだが、偶然にも私の故郷である姫路、それも車で5分ほどの場所に暮らしていたことを聞かされ、うれしい驚きとともに、さっそく手作りの棚に並んだガラス製品を見てまわる。
と、言いたいところなのだが、奥さまをまじえた会話のほうに夢中になりすぎ、1時間ばかりあっという間にすぎてしまう。普段は出たとこ勝負で、まったく予習などしない人間なのだが、左藤さんのブログのすべてと、木村衣有子さんの『はじまりのコップ』を事前に読んでいたことで、ほどよくリラックスして、ガラスに関係ないことまでいろいろ話させてもらう。
途中、中年の男性客がおっかなびっくりあらわれ、くつろいでいた三頭の犬、ユキ、シロコ、クロが大騒ぎのすえ、別の部屋に退場する羽目になったのだが、その後無事、ギャラリーに帰還を果たす。私といえば、ほとんど透明人間のような扱いで、ときどき匂いを嗅がれつつ、床にごろんの、幸せなひとときを過ごさせてもらう。おまけに奥さまに、おひたしにもってこいのオクラの花や、ナスやトマトなどの、色とりどりのおみやげまでいただく。
その後、個展のせまった左藤さんは、すぐそばの工房に入られ、こちらはその伝統芸能の「型」にも通底しそうな、無駄のない洗練された動きを、窓ごしにしばし見学する。オレンジ色の火球に息が吹き込まれ、ふっくらとした縦線モールの、プリーツドレスをまとう一連の流れを、まばたきを忘れてじっと観察する。
購入したのは、以下の二点。
 |
| モール深皿 20センチ |
 |
| ショットワインコップ 8センチ |
モールの外ラインの、ちょうどセンターのあたり、間近で見なければよくわからないのだが、ほんの少しだけくぼんでいる。これがあるのとないのでは、指のかかりがまったく違ってくるはずだ。その工夫がひと目見てわかるような、作為的なものだったら、そこまで感心しなかったかもしれない。あくまでさりげない「実用の美」だからこそ、ささやかな感動が芽生えたのだが、残念なことに、一つだけ懸念がある。つまり、これが単なる、頭でっかちの勘違いである場合、いうまでもなく天狗顔負けの、赤面王子なのである。
【その後のあとがき】
上記の文章を書いてから、早2年がすぎた。左藤さんのコップについていえば、明らかな事実誤認があるのだが、あれこれいじらずに、あえて残しておく。あやまりに気づけたのは、買ってそれっきりではなく、親しくお付き合いさせていただいている証でもあるので。
制作の過程で生まれた「くぼみ」は、おそらく偶然の産物なのだが、かといってショットワインコップの魅力が薄れるわけではない。何度となくマイナーチェンジされ、計算され尽くした、ふちの部分や底の厚み、そして全体としての重さのバランス、シルエット。それらが複合的に合わさって、あの再生ガラス特有の、生きた濡れ感にたどり着くわけだが、それは値札のついたガラスコップという商品でありながら、元手のかかった思索と鍛錬の結実でもある。吹き竿を握るその手には、おそらく小さな火の神様が宿っているはずで、実際、説明のつかない不思議な体験をしたことがある。
あれは2017年の12月、左藤さんを助手席に乗せて、茨城にある前川秀樹さんの工房に遊びに行った帰り道のことだ。ETCの使えない有料道路で、左藤さんは気を利かせ、帰り道だけはその料金を支払うと申し出た。そのさい、室内灯のスイッチをスライドさせたのだが、残念ながらそれは、すでに6年近く壊れたままで、もし直すなら全とっかえの必要があるとディーラーに教えられていた、沈黙の機械なのだった。
もちろんそのさいも壊れていることを伝え、左藤さんは暗闇のなか、何とか小銭を探し、最終的にはツリはいいからと、千円札を私にあずけたのだが、それからひと月ほど経っただろうか、ある日突然、何の前ぶれもなく室内灯が息を吹き返したのだった。
ありがたいことに、それはいまだ現役で、息切れすることもなく、ドアの開閉のたびに元気よく明かりを灯している。『遠野物語』に目がない左藤さんのことだから、きっと光の届かない後部座席のすみっこあたり、小さな火の神様がちょこんと腰かけ、いつ出番がきてもいいように、息をひそめて微笑んでいるはずなのだった。
2018年8月