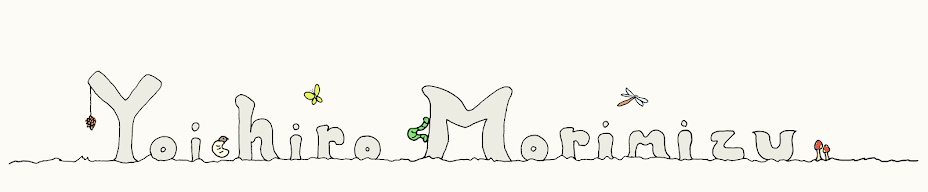8月某日、土屋仁応さんが取り組まれた新作の彫刻を見に、上野の東京都美術館を訪れる。
急遽予定を変更し、人魚や獏(ばく)などの小品が展示された部屋で、息をつめて1時間ばかり過ごしただろうか。これはとんでもないものを目撃したぞという嬉しい震えと、この作家はこれ以上のものを今後作り続けることができるのだろうかという余計な心配で、胸がいっぱいになったことを、昨日のことのように覚えている。
仙川にあるふらんす堂での、詩集の最終打ち合わせの帰り、日本橋の三越で催されていた新作の展示販売会に、ふらりと立ち寄ったのだが、なんとその場に、土屋仁応さん本人がいらしたのだった(たしかツイッターでの在廊告知はなかったはず)。
販売会初日にもかかわらず、すでに一点だけを残して、すべての作品に売約済みのシールが貼られているその人気ぶり。決して手ごろな価格とはいえないのだが、作品のできばえと求心力をかんがみると、当然といえば当然である。
これは彫刻家にかぎらず、素晴らしい仕事を残した人の多くにあてはまると思うのだが、やはり土屋さんも、きわめてひかえめなお人柄で、どことなくほがらかな、相手の緊張をするりととく、独特の空気をまとっておられた。
こちらといえば図に乗って、ここぞとばかりに質問攻め(彩色の仕方や、今後向かわれる作品について)、よせばいいのに、土屋さんの小品「麒麟」が、個人取引のオークションにかけられていたことまで、べらべらしゃべってしまった。ハレの場にそぐわない、まったく余計な蛇足の告げ口である。もちろん土屋さんは、「少し残念ですね」とおっしゃるだけで、「その人も、あなたも」などとは決して言わない。
しかしこの話には、実は私なりの土屋作品への思いがあったのだが、その場ではうまく言葉にできなかった。つまり、少しばかり無理をして、たとえ運よく入札できたとしても、骨身を削る思いで作品に取り組まれた土屋さんには、一銭たりともその見返りがもたらされない。格好をつけるわけではないが、それはなんだか道筋が違うぞ、創作者のはしくれとして、まっすぐに目を見れない恥ずべき行いだぞと、そのような思いが根底にあり、いくらか歯噛みしつつ、入札を見送ることにしたのだった。
(結局その作品は「未入札」で、気が変わったのか、その後まったく姿を見かけない)
本当ならその場で、びしっと端的に説明し、最後の作品をスマートに購入できればよかったのだが、残念ながら私はアラブの石油王ではなく、どちらかというとオケラの二等兵だ。飛んできた銃弾がするりと貫通する、ぺらぺら財布の持ち主だ。
後悔先に立たず。ほどなく、閉店案内の甘ったるい音楽にせかされるかたちで、あたふたと礼を述べ、早くも自己嫌悪の氷雨(ひさめ)に降られつつ、その場をあとにしたのだった。
お前はいったい何をしているんだ。
今日まで何をしてきたんだ。
これから何をするつもりなんだ。