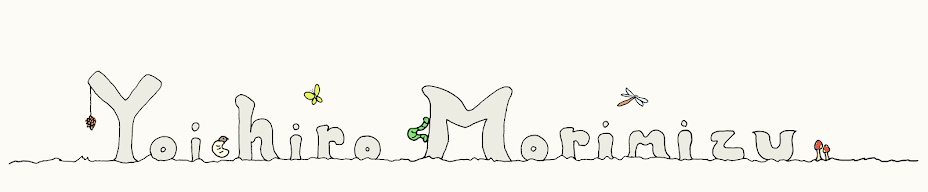10月3日の朝日新聞・関西版(夕刊)に、小野十三郎賞の受賞インタビューが掲載されました。
いすみ市にあるGAKEカフェにお邪魔し、2時間あまりあれこれ話をさせてもらったのですが、当然ながら紙面に丸々おさまるはずもなく。
というわけで、少しばかりの訂正と、補足説明を。
「自分の中の源泉を掘り進める作業」。これは詩にかぎらず、小説にも、普段の生活にも当てはまるような気がします。ときに爪のはがれを伴いながら、あらたな水の予感を信じ、ひたすら自己の井戸を掘り進める。私にとって書くことは、終わりのない自己鍛錬を意味してもいます。
「作家は同じ文章を書き続けるわけにはいかない」。逆に効率のいい、ある意味「頭のいい」仕事の進め方をしている書き手が少なからずいますが、私はできそうもありません。そこには当然ながら、自己模倣の代償がつきまとい、気づかぬうちに自分の身の丈を縮める危険をはらんでいるためです。
「詩作を始めたのは偶然手に入れた新約聖書がきっかけ」。これは正確に言うと、詩作の「師」であって、きっかけではありません。私は詩人から詩を学んだという自覚はなく、4つの福音書といくつかの手紙から、レトリックやメタファーなどの、実践的なテクニックを学んだ気がします。詩を書き始めたのは、発露のためのビークル(乗り物)が、ただ単に、「詩」というカテゴリーに分類されていただけにすぎません。それは便宜上分類されているだけで、私自身、住み分けの壁を設けてはいません。
「詩作は打ち寄せる波をイメージしています」。これは本詩集『九月十九日』だけにかぎられた言葉で、つまり収録された詩の並びをあらわしており、このページが参考になると思います。
* * * *
「抽象的な言葉の旋律」と、「物語性をはらんだ散文詩」の、大波小波が、交互に際限なく打ち寄せるイメージです。あるいは、心電図が指し示す、鼓動の波形(はけい)にたとえてもいいかもしれません。
* * * *
「終わりは詩のほうが勝手に決めてくれる」。もちろんよく耳を澄ませないと、その声を聞き逃し、うっかり書きすぎたり、へその緒がからまったような難産の推敲を迎えたりします。しかし多くの場合、とくに詩にかぎっては、初稿の段階で、それが「詩」の高みに至っているのか、すべてが否応なく決まってしまうように思います。
というわけで、つらつらと補足説明を書いてきましたが、1つだけ残念なことがあります。
実は私の写真、胸のあたりにGAKEカフェの二代目看板猫、Lay(レイ)君を抱いているのですが、どうやら無慈悲なカニの洗礼に遭って、チョキンとやられてしまったようです。
ヘミングウェイや漱石への道は、まだまだ遠く、というところでしょうか。
(※蛇足ですが、新聞記事を許可なくアップロードすると、著作権の門番が怒鳴り込んできますので、ご注意を)
(※蛇足ですが、新聞記事を許可なくアップロードすると、著作権の門番が怒鳴り込んできますので、ご注意を)